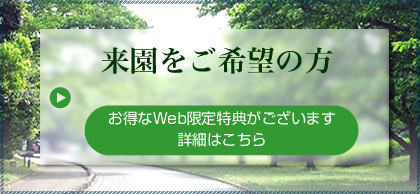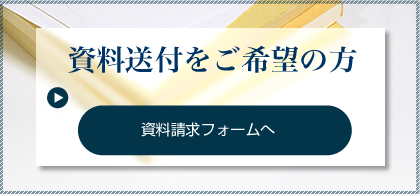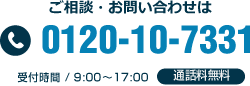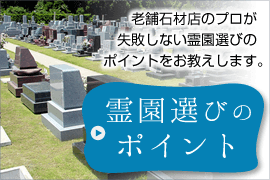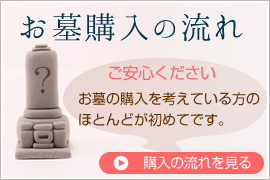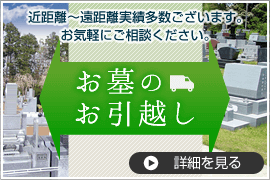霊園にお墓を建てることを考えているが、その場合の檀家制度はどうなるの?と、お考えの方に、霊園にお墓を建てる場合の檀家制度についてご紹介いたします。
 檀家とは
檀家とは
まず、檀家についてご紹介いたします。檀家とは、寺院にお墓のある家のことを指します。一方、お墓を寺に持ってないけれども、そのお寺の宗教に従っている家(人)を信徒と呼びます。
檀家の語源はサンスクリット語の「ダーナ」であり、「お布施」を意味します。
つまり、檀家として寺院にお墓を建て、寺院にお布施をして経済的にその寺院を支える代わりに、お寺の人にお墓の管理や供養をしてもらうということになります。
これが「檀家制度」です。
檀家制度を使用した場合、お墓の管理や供養を手厚くしてもらえたり、葬儀や法事の際にいろいろと助けてもらえたりといったメリットがあります。
この制度はキリスト教徒根絶を目的として江戸時代に始まり明治時代に廃止されましたが、現在でも残っています。最近ではこのような制度を見直す気運もありますが、基本的には日本各所でこうした制度が残っています。
 霊園の場合には
霊園の場合には
結論から申し上げますと、霊園の場合には、檀家制度を考える必要はありません。
霊園は一般的に宗教自由の共同の墓地として認知されます。
従って、檀家制度のような寺院からの縛りも無いということになります。そもそも、檀家制度自体が法的拘束力のあるものとは言えません。
確かに檀家になった場合、手厚い供養が受けられるなどのメリットがありますが、最近の日本人は無宗教の人が多く、そこまで手厚い供養は必要ないと考える人も少なくありません。
また、寺院へのお布施が経済的に負担となり、そういった縛りのない霊園への改葬を行う方も増えています。

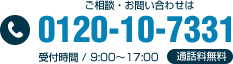
 檀家とは
檀家とは